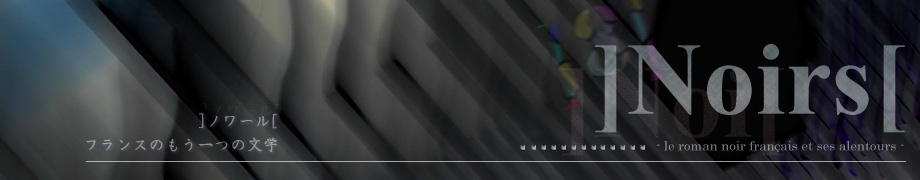 |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
 |
||||
|
|
|||||
|
【1】 |
|||||
|
始まりはこんな感じだった。 |
|||||
|
数時間前のこと。部屋で一人静かに『刑事デリック』を見ていると友達のヴァンサンから興奮した声で電話があった。 |
|||||
|
はいはい、了解。刑事デリックは割と良い場面だったのだけれど、アイルランド娘がいるときたら逆らう訳にはいかなかった。2分後、僕は通りに下りて飲み屋の方角に向かっていた。 |
|||||
|
外は薄暗がりで少し肌寒かった。夏だったのだけれど「これって11月だろう」と言いたくもなる。一つ違うのはパリの通りなのに人通りが全くなかったこと、11月ではありえない話だった。 |
|||||
|
天気と人口の微妙な関係に思いをめぐらせてから飲み屋へと踏みこんでいく。半ば泥酔したアイルランド女性二人と一緒に座っているヴァンサンの姿が見えた。確かに。ただし二人ともお袋と同じくらいの年代だった。自分をぶん殴りたい気分である(熟女好みをどうこう言うつもりはないのだけれど趣味を共有できるのかというと微妙。僕的には穏やかな性格で男馴れしていない女の子の方が好き)。「せっかく来たんだからビールでも引っかけていくか」、自分にそう言い聞かせた。 |
|||||
|
4杯飲み終えた後、ヴァンサン君はアイルランド女の片割れの顔に唇を押し付けていた。僕は相方の女性エリンさんに飼い犬の写真を見せてもらっていた。シシーという名前の毛の短い小犬だった。ビールをもう一杯、エリンさんの舌先が僕の喉元で何をしているのかそろそろ考え始めていた。 |
|||||
|
エリンさんには言っておいた。「もう帰らなくちゃ。片付けないといけない用事が」。これは嘘だった。「手持ちにお金が全く無いのです」。これは本当だった。エリンさんは「晩御飯一緒にどう。明日アイルランドに戻るんだけど、最後に美味しいフランス料理を食べておきたいの。美味しいワインも一緒にね」。それで残るはめになった。 |
|||||
|
ヴァンサンと一緒に王子様のようにたらふく飲み食いした。小綺麗なカフェ・レストラン、目で合図すると料理がやってくる。支払いは完璧に酔っ払ったお姫様たちだった。 |
|||||
|
食べ終わってからヴァンサンが二人に尋ねていた。「クスリで弾けるってのはどう?」。ヴァンサンは超凄のエクスタシーを売ってる男を知っていた。「あまり安くはないのですが」。アイルランド女性二人組はにこやかにお金を並べてみせる。 |
|||||
|
僕は薬はやらなかった。ビールを飲みつづけている。エクスタシーは前に止めていた。ラリッていくのに体が耐え切れなくなっていた。 |
|||||
|
彼女たちが泊まっていたホテルにお邪魔する。サン・ラザール近くの相当上品な建物だった。僕はエリンさんの部屋に。ヴァンサンは相棒の部屋に。 |
|||||
|
エリンさんの瞳がチカチカしていた。「今とっても幸せなの」って。 |
|||||
|
ギュッと抱きしめられた。でも手遅れだった。僕の方が全然だった。だから正直に言っておいた。「飲みすぎでセックスは無理なのかな、と」 |
|||||
|
彼女は「気にしないで」。それから二人で長話。何の話か思い出せないのだけど悪くなかった。二人で一緒に泣きだした。理由は分からない、でもこれが気持ちよかった。 |
|||||
|
最後は彼女の胸に顔を埋めて眠ってしまう。 |
|||||
|
|
|||||
|
ドアを叩く音で目を覚ます。僕一人だった。ドアを開くとルームサービスの女性だった。「はやく出てくださいね」。頭の中に腐った木片があったのだけれど、それでも服を着てホテルの部屋を出た。 |
|||||
|
1階のレセプションホールで受付の男性に声をかけられた。聞こえなかった振りをして足早に通り過ぎようとした。でも向こうはまだ名前を呼び続けていて、カウンターを離れてこちらまでやってくる。「何もしてません」、男を直視して言いかけた瞬間、分厚い封筒が差し出された。「清算をされた女性が渡してくださいとのことでした。良い一日を」 |
|||||
|
通りに出てから開封。何のことやら。札束だった。百ユーロの束。伝言が一つ。目を通してみたがこちらも何のことやら。書いたのはエリンさん。「昨晩はありがとう」。僕の余りの弱々しさに胸を打たれたそうである。「これはプレゼント代わりです…」 |
|||||
|
一番最初に目にとまった喫茶店に入っていく。生ビールを頼んでからトイレに直行。紙幣を数えてみた。1500ユーロ。たったあれだけで。どうかしてるって。 |
|||||
|
ビールをあおると少しスッキリした。ヴァンサン君に電話を入れてみる。家に帰っていた。会って話をしないといけなかった。 |
|||||
|
「ウーラ、おったまげた」がヴァンサンの第一声。「お前さん何かした?」 |
|||||
|
それから「このお金、どうしようか」の相談事。ヴァンサンが名案を思いついた。 |
|||||
|
「ヴァカンスってどうよ」 |
|||||
|
ネットで調べてみた。一人500ユーロでメキシコ一週間の旅を見つけ出す。全て込みの金額だった(飲み放題でいつでもオープンバー状態。楽園の一歩手前って奴)。 |
|||||
|
かくして僕たちはメキシコ湾へと上陸したのです。 |
|||||
|
|
|||||
|
【2】 |
|||||
|
旅日記 |
|||||
|
一日目: |
|||||
|
二日目: |
|||||
|
三日目: |
|||||
|
四日目: |
|||||
|
五日目: |
|||||
|
バーに入っていく。暑かった。演奏団がいる。郷に入れば郷に従え、タコスを食べてマルガリータを飲んでみる。 |
|||||
|
次のバーに入っていく。女が歌っていた。ありえない恋に落ちた。悲しい気分だった。たやすく手に入る女性ではない、無理なのは分かっていた。マルガリータを飲み続けて女のことは忘れ去ってしまう。 |
|||||
|
六日目: |
|||||
|
汚い地面にへたりこんだ。泣きたい気分。今度は何をしたのでしょうか。 |
|||||
|
一時間経過。絶望的な気分。「家にいればよかった」の独り言が漏れる。「静かに刑事デリックを見ていればこんな事には…」。朽ち果てるまでここで生き続ける。5年経って死が宣告される。遺体なしで葬儀が執り行われる。墓石には「アクセル・C。作家に成り損ねた男。メキシコの留置所にて死亡。誰にも知られることなく」の文字。 |
|||||
|
そうはいかなかった。 |
|||||
|
ヴァンサンがホテルで目を覚ます。僕の姿が見えないのに気がついてホテル支配人の元に足を運ぶ。「プールに吐いてごめんなさい」。支配人に助けを求めた。支配人は警察署に直接連絡を入れる。該当人物に心当たりがないかどうか確認を取った。警察署の回答は「あります。留置所から出るには150ドルですね」。車のボンネットによじ登って歌っている所を逮捕されたのだそうな。 |
|||||
|
ヴァンサンが金を手にやってくる。ひげ面の刑事さんが留置所入口を開いてくれた。 |
|||||
|
「靴と荷物はどこにいったのでしょうか」。ひげ男は微笑を浮かべながら「見つけた時にはこの状態でね。街で盗まれたのではないのかな」の返事。嘲るような笑い。同僚の警官たちも嘲り笑いで追随。 |
|||||
|
署を離れる。焼けるようなアスファルトで足の裏が燃えていた。ヴァンサンが靴を片方貸してくれた。二人で片足ケンケンしながらタクシーを探していく。 |
|||||
|
「フランスだったらさ、拘留が終わった時にせめて手荷物くらい返してくれるのにね」、ヴァンサンに言ってやった。「フランスの警官万歳、フランス万歳!」。友人の回答は「まだ酔ってるな」。おっしゃる通りだった。 |
|||||
|
ホテルに立ち寄ってから再び街に向かう。 |
|||||
|
バーをはしごしていく。まだ気が立っていた。それが吉と出た。暗い目をしたメキシコ女を相手に盛り上がった。尻が感動的だった。女をホテルへと連れて帰る。 |
|||||
|
七日目: |
|||||
|
日が落ち始める。ヴァンサンがアイルランド人の一団と仲良くなった。連中はテキーラ飲みのコンテストを開催中、いつものことでヴァンサンが勝者になった。 |
|||||
|
僕はグループの一女性と話しこんでいた。薬物で逝ってしまっていて瞳がチカチカしている。気がつくと女の部屋にいた。キスをしてきた女、でも僕の方が死んだ状態だった。 |
|||||
|
|
|||||
| Mes vacances ou le mythe de l'éternel retour / Axl Cendres in Revue Noir et blanc http://revuenoiretblanc.blogspot.com/ 2007/08/une-fille-frange.html |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
] Noirs [ - フランスのもう一つの文学 by Luj, 2008 - 2010 |
|||||
|
|
|||||