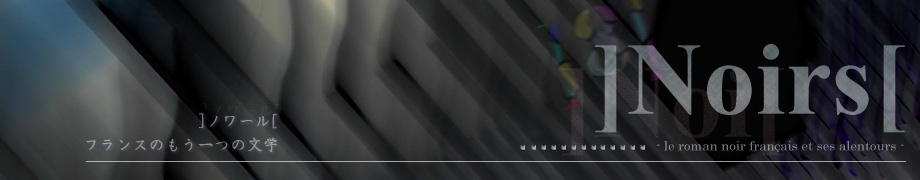 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
僕の軌跡が何か特別だとすれば90年の『リスボン、最後の余白』からではなく85年の『ジュリアン・ミュルグラーヴ比較伝』以来、文学の観点から見た物語世界が続いていることなんだと思う。「SF」があってその後に「純文学」が来たわけじゃないんだ。[註1] |
|||||||||||||||
|
アントワーヌ・ヴォロディーヌ・インタビュー |
|||||||||||||||
|
『軽蔑の儀式:モルドシェール、もうひとつの物語』はヴォロディーヌにとって3作目にあたる長篇で、SFの枠組みで発表された初期作の一つとなっています。この作家のSF期については現地でもめったに触れられることのない話題ですので、周辺状況を含めた足取りを簡略に追ってみるのも良いのではないかと思います。 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
80年代中盤の仏SF界ではまさに「新しいSF」が話題となっていました。J・G・バラードやP・K・ディック(さらにジャンル外のバロウズやピンチョン)らの作品創造を踏まえ、単純な善悪の二元構造を廃し、旧来のスペースオペラと袂を分かった興味深いSF作品がフランス語に訳され、認知されていった時期に当たります。 |
|||||||||||||||
|
『ニューロマンサー』、『スキゾマトリクス』…後にサイバーパンクの名で一括されていく文芸潮流ですが、ここには純文学とジャンル文学の境界を曖昧にしていく動きも含まれていました。ブルース・スターリングは自作を含め、メインストリームとは異なったオルタナティヴな文学に「スリップストリーム(傍流)」[註2]の形容を与えていたのですが、それは後に「ポストモダン文学」と呼ばれた何かと瓜二つだったりもしています。 |
|||||||||||||||
|
ギブソン、スターリング、ルディ・ラッカー、グレッグ・ベア他を収録。サイバーパンク初期のショーケースとなった短編集『ミラーシェード』のフランス語訳が公刊されたのが87年初頭、出版元はドゥノエル社、叢書「未来の現れ」の第451番でした。 |
|||||||||||||||
|
フランスでこの辺の作品紹介を進めていたのは「未来の現れ」監修者エリザベス・ジルで、彼女は『ミラーシェード』の次の452番に仏作家の短編アンソロジー『世界に逆らって』を持ってきました。「リミット」というグループ名の下で新進SF作家7名が2編ずつ寄稿、この中にヴォロディーヌが顔を見せています。 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
英・米語圏の新しい動きにフランス語圏の新世代作家を対置させる。エリザベス・ジルの判断、選択は間違っていなかったと思いますが…『ミラーシェード』との読後感は大分違っています。テクノロジーやサブカルチャーに対する関心が希薄な一方、20世紀実験文学(カフカやジョイス、セリーヌやバロウズ、ヌーヴォーロマン、現代実験詩)の影響が強く押し出されています。『世界に逆らって』に参加したメンバーで有名な4人を挙げておくと: |
|||||||||||||||
|
1) フランシス・ベルテロ(80年デビュー)。「リミット」の理論的中核、知性派。宮沢賢治を想起させる鉱物質の綺想で書かれた『目の奥の街』、バイセクシャル時代の悲恋を寓話化した『触れえぬ者たちの岸辺』が代表作。 |
|||||||||||||||
|
2) シュールレアリスム寄りの幻視を得意としていたのがエマニュエル・ジュアンヌ(82年デビュー)。特殊な残酷劇に触れることもあり、後にはスプラッター系の作品にも進出。長篇第二作目の『雲』の評価は現在でも高いです。 |
|||||||||||||||
|
3) ジャック・バルベリ(85年デビュー): ディック、バラード以後の問題設定を乾いたハードボイルド・タッチで描いていくのに巧み。 |
|||||||||||||||
|
4) アントワーヌ・ヴォロディーヌ(85年デビュー)。 |
|||||||||||||||
|
まだほとんど無名だった若手作家が意気投合し、議論を重ね、SFや文学について思いを馳せ、文芸集団「リミット」を形成したのは86年末のことでした。 |
|||||||||||||||
|
ジュアンヌの『此岸』が84年のロスニー・エネ大賞、ベルテロの『目の奥の街』が87年の同賞を獲得。ヴォロディーヌの『軽蔑の儀式』が今度は87年の仏SF大賞を受賞…こう並べていっただけでも局所的な盛り上がりは伝わるのではないかと思います。新しい潮流に同調するように他作家(コレット・ファイヤール、フィリップ・キュルヴァル)が合流を表明、短編集第2弾の構想が膨らんでいきます。 |
|||||||||||||||
|
順風満帆とはいきませんでした。純文学(あるいは実験文学)の方法論、発想を持ちこまれるのを快く思わないジャンル愛好家も多かったからです。 |
|||||||||||||||
|
1988年夏、ヴォロディーヌとベルテロはケベックで開催されたSFシンポジウムに参加、ここで集中砲火を浴びます。「こんなのSFじゃない」。伝統と型を持つジャンルからの手厳しい反撃です。リミット周辺作家をサポートしてきたエリザベス・ジルが監修職を退いたのも大きな痛手でした。88年、「リミット」は第2アンソロジーを刊行することなく解消、ヴォロディ−ヌも同年の『夢のような地獄』を最後にドゥノエル社を離れています。90年発表となった次作(『リスボン、最後の余白』)は仏インディ出版社の雄ミニュイから。『微弱天使』へと伸びていくゆるやかなサクセス・ストーリーの第一歩ですが、ここからはまた別な物語になっていきます。 |
|||||||||||||||
|
2006年、「リミット」の結成から20周年を記念したCDブック『音の果てに』が発売されています。SF+ポエトリー・リーディング+実験音楽の発想で作られた朗読短編集。オリジナルメンバー7名の内6名が参加。唯一参加しなかった不義理者はヴォロディーヌです。群れて動くタイプの作家ではないので驚きはしませんでしたが…あの孤独な異端幻視者が20年前のリミットに参加していた事実の方が今となっては意外なくらいではないでしょうか。 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
冒頭に引用したインタビューから察すると、ジャンル文学での出発を振り返る作家の視線に特別ネガティブな感情はないようです。ヴォロディーヌ作品を特徴付けている諸々のファクター(終末論的風景、歴史の記憶、夢想による世界の変容、コミュニケーションの不可能性、迫害妄想と疎外感、畸形生物への憧憬・共感・同一化…等々)はそのまま初期作品にも見て取れるものです。現在との違いは幻想や妄想の深さ、そしてそれらを呪われた「美」へと昇華していく技術の部分になるでしょうか。 |
|||||||||||||||
|
ここでもう一度「リミット」に戻ってみる必要があります。ヴォロディーヌやベルテロ、ジュアンヌといった作家たちは一括してリミット「派」と呼ばれることがあるのですが、それとは別に「ネオ・フォルマリズム」「形式主義的SF」の形容をされることもあります。 |
|||||||||||||||
|
作家たちは全く何も語るべきものを持っていなかったのだけど、それでも時にありえない厳密さと美しさで文章をつむぐこともあった(ヴォロディーヌ、ジュアンヌ)。「ネオ・フォルマリズム」のレッテルを貼られたこの手の作家たちが、リミット派という形で結晶化していく。[註3] |
|||||||||||||||
|
SF作家ミシェル・パジェル。 |
|||||||||||||||
|
ここでの「形式主義」は批判的な意味合いで使われています。物語が明快なつながりを持たず、場面や人物が曖昧なまま、言葉と意味が遊離したような作品を前にしたとき、作品としての「内実」「中身」が希薄でその外側の「言葉」だけを相手にしているような気がしてくる。内容vs形式の二元論で言えば後者に比重が置かれている。読み手のそんな(時に苛立ちのこもった)体感を一語に閉じこめたとき、「形式主義的SF」のような悪意のこもった形容が生まれてきます。 |
|||||||||||||||
|
書き手の思惑は別なところにあります。言葉が明快に一つの意味対象を持つ、そんな常識を保留したときに生まれてくる言語のカオスをいかにして効果的、魅力的な「形」に組み立ててていくか、そんな風に動いていく作家もいるということです。ロシア・フォルマリズムに対するヴォロディーヌの共感はよく知られているところですが、それだけにとどまらず97年の架空文学理論書『ポスト・エキゾチスム10講、その第11講』で「フォルマリズム」に独自解釈を与えている[註4]くらいです。 |
|||||||||||||||
|
ヴォロディーヌ型フォルマリズムの一例として、単語数や章数による制約を挙げることができます。『ヴァルキリーの白夜』(97年)と『微弱天使』(99年)はそれぞれ49章構成で書かれていますが、作家にとってこの49は「秘数、タントラの数」に当たっています(1949年生まれの作家にとって特別な数字でもあるのでしょうが)。 |
|||||||||||||||
|
単語数の制約はもっと徹底していて: |
|||||||||||||||
|
A: 「シャガ(7詩篇)」と呼ばれる独自形式の散文詩は7つの詩篇それぞれが666語で完成される形になっている。 |
|||||||||||||||
|
B: 「ミュルミュラ(囁物語)」と名づけられた独自形式の短編では、作品の総単語数が777語となるように調整されている。 |
|||||||||||||||
|
C: 「ロマーンス(長物語)」と呼ばれる独自形式の長編では、作品の総単語数が66666語となるように設定されている。 |
|||||||||||||||
|
読者は単語数など数えない、章数など気にしない。当然の前提を受入れながら作家は一人黙々とカウントしていきます。ここで発動しているのは怪しげな数秘術ではなく、「文字数で強制的に縛りをかけないと言葉、物語が拡散してしまう」の危機意識から生まれてきた文学的戦略なのです。 |
|||||||||||||||
|
言葉のカオスに秩序と形式美を与えていく。 |
|||||||||||||||
|
章段の対称性を意識した『納骨堂俯瞰』や『微弱天使』では「断章の組み立て方が綺麗だな」と思わせるレベルにまで到達しています。果たしてこれを「フォルマリズム」と呼べるのかどうか疑問ですが、リミットの段階で発現していた問題設定がそのまま90年代の純文学期に引き継がれていった一つの例になっています。 |
|||||||||||||||
|
ヴォロディーヌ作品が妖しげな魅力を放つのは言語実験と幻視の力が綺麗な「形」まで磨き上げられた時です。80年代は模索期の印象が強いのですが、中でも第3長篇の『軽蔑の儀式』はこの試行錯誤が上手く結実した作品として知られています。 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
1) 尋問劇の設定を口実とし、懐古風の口調を交えながら「家族の肖像」(両親、伯母、伯父、従兄弟…)を紡いでいく物語レベル。 |
|||||||||||||||
|
2) 隊長オプチェンコを狂言回しとし、戦争小説(或いは「対=異星人」というSF紋切型)をトレースし、歪めていく物語レベル。 |
|||||||||||||||
|
3) 歴史記述と思弁考察を組みあわせ、物語の背景を説明していくレベル。 |
|||||||||||||||
|
『リスボン、最後の余白』でもやはり3層型の構造が使われていましたが、物語レベルの各層はさらに複雑な入り組みを見せていました。『軽蔑の儀式』ではそこまで複雑なインターテクスチュアリティーは使用されておらず、結果として全体が明快で読みやすい形となっています。 |
|||||||||||||||
|
柔らかめの叙情が強調された『軽蔑の儀式』、幻視の破壊力を突きつめた『リスボン、最後の余白』、構成美で際立った『微弱天使』。単純化するとこうなるでしょうか。ヴォロディーヌ史の全体を貫いている「フォルム」への強い自覚は86年末、「リミット」結成の段階から既に発動していたものだったのです。 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
【原注】 |
|||||||||||||||
|
〔1〕: Or, s'il y a singularité dans mon parcours, c'est bien
parce que je revendique la continuité littéraire de mon univers,
nonà partir de Lisbonne, dernière marge (Minuit, 1990), mais
à partir de Biographie comparée de Jorian Murgrave (Denoë?l,
1985). Il n'y a pas eu "de la SF" puis "de la littérature".
|
|||||||||||||||
|
〔2〕: Slipstream (1989) / Bruce Sterling |
|||||||||||||||
|
〔3〕: C'est à dire que les auteurs n'avaient strictement rien à dire, mais cela ne les empêchait pas de ciseler leurs phrases avec une précision et une beauté extraordiaire(Volodine, Jouanne). On les a regroupés sous l'étiquette du "Néo-formalisme", (ce qui veut tout dire!) qui a trouvé sa concrétisation dans l'école "Limites". |
|||||||||||||||
|
〔4〕: 「シャガ(7詩篇)に見られる正典モデルはロマーンス(長物語)には存在していない。とは言え、最初のロマーンスである『微弱天使』の発表時点から形式主義の側面が現れていたと言う事はできる。韻律や音楽に関わった配慮は作家が遵守すべき制約の一部となっていたのである。 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
【書誌 (『軽蔑の儀式』以外。英語作品に関しては仏初訳)】 |
|||||||||||||||
|
・『ミラーシェード』 短編アンソロジー |
|||||||||||||||
|
・『ニューロマンサー』 ウィリアム・ギブソン著 |
|||||||||||||||
|
・『スキゾマトリクス』 ブルース・スターリング著 |
|||||||||||||||
|
・『世界に逆らって』 リミット著(短編アンソロジー) |
|||||||||||||||
|
・『目の奥の街』 フランシス・ベルテロ著 |
|||||||||||||||
|
・『触れえぬ者たちの岸辺』 フランシス・ベルテロ著 |
|||||||||||||||
|
・『雲』 エマニュエル・ジュアンヌ著 |
|||||||||||||||
|
・『此岸』 エマニュエル・ジュアンヌ著 |
|||||||||||||||
|
・『ジュリアン・ミュルグラーヴ比較伝』 アントワーヌ・ヴォロディーヌ著 |
|||||||||||||||
|
・『夢のような地獄』 アントワーヌ・ヴォロディーヌ著 |
|||||||||||||||
|
・『リスボン、最後の余白』 アントワーヌ・ヴォロディーヌ著 |
|||||||||||||||
|
・『ヴァルキリーの白夜』 アントワーヌ・ヴォロディーヌ著 |
|||||||||||||||
|
・『納骨堂俯瞰』 アントワーヌ・ヴォロディーヌ著 |
|||||||||||||||
|
・『ポスト・エキゾチスム10講、その第11講』 |
|||||||||||||||
|
・『微弱天使』 アントワーヌ・ヴォロディーヌ著 |
|||||||||||||||
|
・『音の果てに』 共同制作作品(CDブック+テクスト) |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
] Noirs [ - フランスのもう一つの文学 by Luj, 2008 - 2010 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||