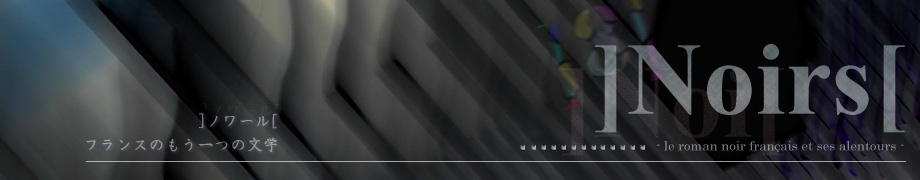 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黒い皇太子の肖像
〔アンドレ・エレナ 1919 - 1972〕
|
|
2008年9月
Tag: 作家ポートレイト。アンドレ・エレナ、暗黒街物
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
かつて「暗黒小説」と呼ばれていた意味での仏ロマン・ノワールを源流にさかのぼっていくと、一方でレオ・マレに代表される40年代の「私立探偵物」が出発点にあり、途中からそこにアルベール・シモナンやジョゼ・ジョバンニ、ピエール・ルスーらの「暗黒街物」が合流してくる形になっています(シムノンは独立した一分野になってしまい後代への影響力は強くありません)。
|
|
|
現在フランス語で手に入るミステリーの入門書、啓蒙書の大半も大筋はこの歴史観、文学史観を踏襲しているのですが、80年代後半からこの見方を若干修正する動きが出てきています。「ロマン・ノワール界の皇太子」ことアンドレ・エレナの再発見、再評価の流れです。
|
|
|
邦訳が手に入る数少ない基礎文献の一つ『ロマン・ノワール - フランスのハードボイルド』(ジャン=ポール・シュヴェイアウゼール著、初版1984年。邦訳:平岡敦、1991年、白水社)では一度も名前の出てこない作家です。同著者が87年にミシェル・ルブランと共著で著した『ガイド・デュ・ポラール(ミステリー・ガイド)』(シロス社)には数度登場、大きな扱いではありませんが5段落に渡って単独での紹介がされています。一部を引用します。
|
|
|
アンドレ・エレナ (1919-1972):
ナルボンヌ生まれ。19才で最初の作品『黄金の環』/詩集を発表。この若さで監督アンリ=ディアマン・ベルジェのアシスタントとなり映画『探偵リュパン』の制作に携わる。
12年後、様々な仕事に手を染めた後に推理小説に挑戦、叢書「黒い夜」に良質な暗黒街小説『刑事が間違うことはない』、『神様は気にしない』を寄稿。
|
|
|
「アンドレ・エレナ」
『ガイド・デュ・ポラール(ミステリー・ガイド)』
144ページ。1987年、シロス社。
|
|
|
|
|
|
エレナは1936年から40年にかけ5冊の詩集を発表。暗黒小説作家としてのデビューは1949年、ワールド・プレス社の叢書「黒い夜」からとなっています。
|
|
|
1949年は暗黒物叢書の乱立が目立ち始めた時期に当たります。最終的にはセリ・ノワール、スペシャル・ポリス、アン・ミステールの3つが生き残り、他叢書は読み捨てられ、忘れ去れられていきます。それがエレナ(あるいはクロード・フェルニやジョルジュ・マクスウェル)の辿った運命でもありました。現在エレナ初期作のオリジナル版を見つけるのは極端に難しく、古書マーケットでは時に一冊70〜100ユーロ(1万〜1万5千円前後)で取引されていたりもします。
|
|
|
50年代のエレナは執筆に専念、53年の1年間だけで18冊の小説を発表。50年代の後半はディティス社の叢書シュエット、60年代からは叢書スペシャル・ポリスに寄稿。ただしこの時期になると生活費を稼ぐため量産している感もあり、後からデビューしたノワール作家たちに名実共に差を付けられた形となってしまいます。
|
|
|
80年代になって再評価開始。ウィリアム・アイリッシュ作品の翻訳などで知られている10-18社がエレナ旧作を発掘。処女長編『刑事が間違うことはない』が35年ぶりに再刊されました。
|
|
|
この後エレナ作品は再版〜絶版を繰り返していきます。90年代中盤にはフロラン・マソ社。『ベーズ・モワ/馬鹿な奴らは皆殺し』で有名になった出版社は『神様は気にしない』を忘れてはいませんでした。00年代になると今度はE-ディット社が書誌、序文を付した丁寧なエディションに取り組んでいきます。
|
|
|
作品の普及に伴い専門誌でも特集が組まれていきます。2000年から01年、リヴァージュ社のポラール誌は2号連続(23〜24号)でエレナ特集を敢行。813協会がやはり01年5月発表の機関紙(76号)でエレナを扱い、同年夏にはミステリー小説図書館(Bilipo)で展覧会が開催されています。
|
|
|
|
|
|
アンドレ・エレナの完全復権は今世紀、2001年になってからでした。半世紀に渡って眠り続けた作品がようやく再発見されつつあります。20年間に及ぶ執筆作業で200作を越える作品を発表、現在その1割が市販で入手可能です。幾つか作品名を挙げておきます。
|
|
|
・ 『刑事が間違うことはない』 (1949年)
・ 『神様は気にしない』 (1949年)
・ 『サルヴァドールを殺ってやる』 (1949年)
・ 『英雄は気にしない』 (1951年)
・ 『夜のめぐりあい』 (1952年)
・ 『未亡人にキスを』 (1953年)
・ 『血の味』 (1953年)
・ 『ピガールに落ちる』 (1958年)
・ 『金曜の旅人』 (1958年)
・ 『スペインの馬』 (1959年)
|
|
|
なぜ今、21世紀にアンドレ・エレナなのか。半世紀に渡って過小評価されつづけてきた作家であり、現代作家への影響は微弱なものです。根強い信奉者を生み出してきた訳でもありません。エレナを「ノワール小説名匠の一人」を呼ぶ根拠は別にあり、それを3つに大別できるかと思います。
|
|
|
1) 「罪の都パリ」を生きた内部証言として
2) 権力の横暴に逆らった抵抗の士として
3) ある種の「リミット」を越えた特殊な作家として
|
|
|
3つの視点、切り口はエレナ著作の内部では必ずしも矛盾してはいません。何を期待し、どの要素を強調するかで異なった作家像が見えてきます。それぞれを簡単に説明していきます。
|
|
|
|
|
|
50〜60年代産の暗黒小説が根強い愛好家を抱えているのはある時代、ある特殊な社会、ある特殊な感性と価値観を反映しているからです。しばしば「その筋(ミリユ)」で集約されてしまう何かですが、必ずしも犯罪「者」の世界だけを指すわけではなく、同時代の事物や都市風景、細かな言葉遣い、感情の表現形、人々の立ち振舞いまで含みこんでいます。
|
|
|
1957年に発表された『ピガールに落ちる』は歓楽街を牛耳っているコルシカ・マフィア、アラブ・マフィアの抗争を背景とし、弁護士ルーセル、対アラブ特捜班を交えた四つ巴の物語を紡いでいきます。この作品に登場する「カイード」=「チンピラ」、「ドゥミ・セル」=「半端者」はいわゆる「マフィア」には似ていません。
|
|
|
ピンボールの玉を弾いたティノ。金属の玉は左右に行ったり来たりの弧を描き、一瞬ためらいを見せ、迷うことなく盤面の下へと落ちていく。
チャンスを逃した気分だった。運勢を呼び戻そうと機械の両脇を拳で叩いてみる。玉が飛び出してくるかもしれなかった。チーンという音が一度、画面が真っ暗になる。小さな四角が光っていて「エンド」、無慈悲な言葉だった。
呪いの言葉を一つ。男は握りこぶしを振り上げ、周りの連中を追い払うと立ち上がった。
ガラス窓の先を横切ろうとしたモハメドの姿に目を留める。いつも通り穏やかで自信満々の様子だった。
ティノは隣にいた仲間の腕に手を置いた。
「ここで待ってろ。すぐ戻ってくる」
「何処行くって?」
「奴に借りを返しておこうかな、と」
|
|
|
『ピガールに落ちる』
第4章、47-48ページ。
再版2002年、E-ディット社。
|
|
|
オンラインゲームもDVDも無かった時代、ピンボールで退屈を紛らわせているコルシカ青年たち。「ビストロのピンボールマシーン」を「駅前のゲームセンター」に、名前を日本風に置き換えてしまえば現代の小説でも違和感のない一節です。物語はすぐ「カミソリの刃」に向かうので確かに「犯罪小説」ですが、引用部分だけを見ればある種の青春群像。特別な「掟」に従い組織犯罪で利益を上げているマフィア一員を描いているようには見えません。
|
|
|
エレナの視点はこの場面を内側から、登場人物と同じ高さの目線で切り取っています。この視線には親しみ、共感、仲間意識が含まれています。
|
|
|
コルシカからにせよ中近東、北アフリカからにせよ、パリに流れてきた人々は「犯罪組織」を作るために集まったのではなかったはずです。同郷の士による互助的なコミュニティーがいつしかマフィアと呼ばれ、実際に犯罪組織と化していきます。『ピガールに落ちる』が描き出していたのは「一般人以上、マフィア未満」、この境界線上に位置する者たちでした。
|
|
|
ここには犯罪社会を「美化」する発想が欠けています。ピエール・ルスー(『犬』、『鉄の点』)のように半端者の「美学」をロマンチックに強調してみせるのではなく、手の届く場所にいる人々の犯罪模様を描きだし、読み手をその世界に誘っていきます。ルスーの様式美に比べると地味な世界。しかし生き生きとした細部が現代の読み手にもアピールしていく訳です。
|
|
|
エレナの世界に足を踏みこんでみる。40〜50年代の「失われたパリ」を内側から追体験していきます。抗争、ドメスティック・ヴァイオレンス、拉致、密売、薬物、売春、密告…作中で発生している出来事は暗い内容ばかりですが、奇妙なことに悪人たちはそれほどの悪党顔はしていません。読み手もまたそれを過去の虚構と割り切って雰囲気を楽しんでいきます。
|
|
|
タクシーは人気のない通りを抜け、不意に色鮮やかで目の眩むような光のオーロラに姿を現した。湿り気を帯びた霧の中、タクシーの薄暗い席に座っていたアリーヌは輝いている舞踏曲で回り始めた気分だった。
通りはいつの間にか人でごった返していた。舗道に沿って、影たちは「夜は終わらない」とでも言いたげにゆったりと流れ続けている。そして霧の先からはナイトクラブの賑やかな音楽が。
|
|
|
『ピガールに落ちる』
第1章冒頭部、11ページ。
再版2002年、E-ディット社。
|
|
|
エレナは往時の歓楽街、夜の描写を得意としていました。「昔は」の感性に強く訴えかけてきます。実際、時代に関わらずエレナを擁護し、その復権に取り組んできたのはこのノスタルジックな保守層でした。作家の忘却を妨げてきた意味で非常に価値のある活動だったと思います。
|
|
|
|
|
|
エレナ作品には全く異なった解釈が存在しています。第2の視点は『刑事が間違うことはない』、スペインを舞台にした2作『サルヴァドールを殺ってやる』、『スペインの馬』の重要性を強調してきます。
|
|
|
『刑事が間違うことはない』は激しい政治意識に裏打ちされ、警察署の地下で起こっている忌まわしい出来事全てを紛れのない筆致で告発してみせた最初のフレンチ・ミステリーの一つである。
|
|
|
「ロマン・ノワールの子供たち」
ジャン・ロラン、1971年。
ラ・リュ誌、第11号。
|
|
|
映画監督・作家ジャン・ロランの手による一節が良い要約になっています。「政治意識に裏打ちされた(アンガジェ)」、「告発」といった用語法は五月革命を経験したフランスのインテリ左派が好むもので、エレナに「反逆者(レヴォルテ)」の姿を読み取っていきます。セリ・ノワール作家パトリック・ペシュロが自身のサイトで『サルヴァドールを殺ってやる』、『スペインの馬』を高く評価しているのも同じ文脈になります。
|
|
|
『サルヴァドールを殺ってやる』はスペイン内戦下、反ファシズム運動に参加した主人公がかつての同士、現在の裏切者を追跡していく物語です。歴史物のようにも見えますが、主人公「僕」が銃を手に「汚いファシスト」を始末にかかる展開はノワール的発想によるものです。
|
|
|
|
|
|
暗黒街の語り部、筋金入りの反抗者。前者で言えばオーギュスト・ルブルトン、後者ならジャン・アミラ。仏ロマン・ノワールは他にも優れた作家を生み出してきたはずです。この二つだけではエレナを説明しきれない不満が残ります。
|
|
|
03年に再刊された『夜のめぐりあい』でジャン=ピエール・ドゥルーが序文に次の一節を残していました。
|
|
|
エレナ作品を手にした読者は知っていたはずの文明世界の究極の限界まで導かれていく。見たこともない何か、野蛮、理性の先に滑りこんでいくには言葉一つ、文章一つで充分なのである。
|
|
|
「犬と狼の間」
ジャン=ピエール・ドゥルー
『夜のめぐりあい』序文、9ページ。
2003年、E-ディット社。
|
|
|
エレナ著作に触れていると確かに時折「危ない領域に踏みこんでいる」の印象を受けることがあります。「リミット(限界点)」の概念を使ってドゥルーが明文化しようとしているのはこの感覚です。
|
|
|
娘は椅子の前に膝をついて座る。
掴みかかった老婆が力まかせに殴りつけた。鞭のような音が一度。倒れこんだ娘、顔が涙でくしゃくしゃになっている。むせび泣きに揺れている背中を無言で殴り続けている。
[…]
うんざりしてきたので手を出すことにした。少女の肩を掴んで立ち上がらせる。 […]
「何?」、老女の叫び声。「あんたもかい。あんたもこの雌犬の味方するってのかい。男を咥えこむしか頭にないこんな女を」
|
|
|
『神様は気にしない』
第4章、56-57ページ。
再版2002年、E-ディット社。
|
|
|
伯母が姪を延々と殴打しています。場末にはこの手の悲惨は幾らでも転がっている、エレナの描写はそんな醒めた筆致になっています。
|
|
|
しかし主人公はこの世界を「観察」しています。時折「手を出す」程度で一定の距離感は維持されています。もう一歩足を踏み出し、主人公自身が不道徳な世界を積極的に引き受け始めた時、当時の仏ノワール小説、仏社会では許されていなかったはずの作品が生み出されてきます。53年に発表された『血の味』がその例です。
|
|
|
舞台は1944年、終戦直前の田舎町ペルピニャン。のどかな町にドイツ軍が進駐してきます。主人公ジャックは司法試験に合格、今頃は法学部で楽しい学生生活を送っているはずでした。独軍の進駐でその夢が費え去ります。未来を封じられた恨み、女から無視されている不満、父親との軋轢、鬱憤をはらすように青年は対独協力者の銃殺にとりかかっていきます。
|
|
|
「金はいらないって?」と男。「なんてこった。お前さん一人じゃないか。お馬鹿さんなことは言わずこの50フラン取っておけよ。何かの役には立つさ。町から逃げる時どうするよ?」
その通りだった。ジャックはそこまで考えていなかった。もし逮捕されたらとは思っていたが逃亡のことまでは。
|
|
|
『血の味』
第3章、32−33ページ。
再版2004年、E-ディット社。
|
|
|
敵の処刑。金目当てでも正義を望んだのでもありません。漠然とした私怨を晴らすためだけに殺していきます。金回りがよくなりはじめ、父親には誕生日のプレゼント、女性関係も好転の兆し。「血の味」を占めたジャックは次第に悪事に深入りしていきます。結局は密告され殺人者として追われるのですが、その途上、自分を密告した女性をレイプし射殺してしまいます。
|
|
|
突然男の表情が変わったのに気がついた。さっき襲いかかってきた時と同じだった。銃身がこちらに上がってきている。
女は立ち上がる。叫ぼうとした。
「や…」
巨大な爆発音。黒、黒、目が眩みそうな黒が。
|
|
|
『血の味』
第11章、216ページ。
再版2004年、E-ディット社。
|
|
|
「社会悪の告発」という口実は消え失せ、「暗黒街」の要素すら希薄となり、全体は連続殺人鬼の栄枯盛衰を追ったルポルタージュになっています。書き手が主人公に同一視しながら書いているため、読み手もまたこの非道徳な世界を否応無く共有させられることになります。
|
|
|
この引用で重要なのは「突然(スダン)」という表現です。エレナ作品の登場人物たちは「不意に」、「突然」それまでと異なった動きをする傾向を持っています。胸の奥、頭の片隅、存在にまとわりついて離れない何物か(「恐怖に満ちた眩暈」)を振り払おうと予期しない行動に走り始め、悲劇をもたらしていくのです。
|
|
|
「見たこともない何か、野蛮、理性の先へと滑りこんでいくには言葉一つ、文章一つで充分なのである」。ドゥルーの序文にあった一節です。些細な出来事、言葉一つで物語が、心が唐突に狂気の側に転調していく。エレナ作品の怖さであると同時に魅力の一つにもなっています。
|
|
|
『血の味』はアンドレ・エレナが最もトンプソンに近づいた一作だと言えそうです。主人公の心性としては『内なる殺人者』、視点を切り替えながら緊張感を高めていく手法は『キル・オフ』を想起させます。だからと言ってエレナがトンプソンに匹敵する作家だという結論にはなりませんが、国こそ違えど同時代に活躍していた作家であり、特殊な心の闇を通じてリンクする部分があったとしても不思議ではない気はします。
|
|
|
|
|
|
エレナは元々は詩人志望でした。戦前に発表された詩集にも後のノワール作家の面影は見え隠れしています。53年〜55年には「アリスト」というリュパンを念頭に置いた怪盗紳士シリーズも手がけています。作家全体像、あるいは可能性の中心を模索していく作業はまだ続きそうですが、いずれにしても仏ロマン・ノワール史を彩った重要な才能の一つという事実は揺らぐことはなさそうです。
|
|
|
|
|
|
【書誌】
|
|
|
・『神様は気にしない』(1949年) アンドレ・エレナ著
Le Bon Dieu s'en fout / André Héléna
- Paris: E-dite. -(E-dite noir). -233p. - 2002.
|
|
|
・『血の味』(1953年) アンドレ・エレナ著
Le Goût du sang / André Héléna
- Paris: E-dite. -(E-dite noir). -239p. - 2004.
|
|
|
・『ピガールに落ちる』(1958年) アンドレ・エレナ著
Descente à Pigalle / André Héléna
- Paris: E-dite. -(E-dite noir). -215p. - 2002.
|
|
|
|
|
|
                   |
|
] Noirs [ - フランスのもう一つの文学 by Luj, 2008 - 2010 |
|