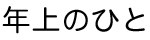
ヒグラシの鳴く夕暮れの道。
日中の熱気を残した地面がゆらりと蜃気楼を上げる、その先に。
「…あんのキツネ、まーたウチの前にいやがる」
見えた黒髪に花道はため息を吐いた。
桜木と表札のかかった扉の下で、流川が気持ち良さそうに寝息を立てている。
学ランにスニーカー、スポーツバックを横に放っている辺り、今日も部活の後そのままやって来たのだろう。
おい、と投げやりに声をかけながら、花道は我が家への進入を遮るそれをつま先で軽く蹴ってやった。
天才的に寝汚い相手だが、花道がそうすると一発で覚醒するのだから不思議である。
「…どあ、ほう…」
「そこどけ。家に入らせろ」
「…キスしてくれたらどいてやる」
ゴスッ!
きれいに頭突きがきまったところで、漸く流川は立ち上がった。痛ぇ、などと言いながらもしっかりと花道の後についてくる。
「今日は冷やし中華が食いてー」
「あほか。んな都合良く麺が用意してあってたまるか」
「昨日冷蔵庫で見た」
「おま…っ、勝手に人んちの冷蔵庫見てんじゃねーよ!」
たまには家に帰れ家に!そう言おうとして花道は口を噤んだ。
ああ、そうだ。そうだった。今こいつん家…。
思いながら流川を見やる。
もはやシャツ一枚でいつもの定位置に座る彼は、つい先日から両親が海外転勤になったのだった。
その事をすっかり失念していた花道。だが、忘れてしまうくらい当たり前にウチに居座る流川が悪いのだ。
責任転嫁して流川を睨む。
「コラキツネ、」
流しで手を洗いながら、いい加減言われる前に手ぐらい洗えと愚痴る花道の横で、渋々となりに並ぶ流川の黒髪が視界の斜め下に過ぎった。
「…ぬ?」
その角度に、花道の肩眉がピクリと上がる。
こいつ、いつの間に…
そんな花道の視線に気付いたらしい。流川はタオルで手を拭うと花道を覗き込んできた。
「なに」
「…おまえ、背いくつだ」
「?春に計ったときは177だけど」
「何ィ!!」
ひゃくななじゅうなな!!177cmだと!?
ついこの間まで160cm台だったはずだ、このガキは。それが…。
信じられない思いで花道は流川の背中に自分のそれを合わせた。ぴたりと密着させて頭の上でひらひらと手のひらを振る。
それをただ傍観していた流川だったが、まだまだオレには及ばんな、と花道が高笑いしたところで急に態度を変えた。即ち、花道に向き直ったのである。
「どあほう」
珍しく、彼は笑っていた。
「そのうち抜く」
流川楓。13歳。中学二年生。
彼が桜木花道と出合ったのは、今から四年前。流川小学四年生、花道小学六年生の時だった。
親の転勤でやってきたという流川は、少年らしからぬ寡黙さと鉄面皮を兼ね備えていて、花道は最初それを、転校続きのストレスからくる感情の欠落だと思っていた。
しかし、いつだったか。
どうやらそれは違うらしいと気が付いたのだ。
確かあの時は…。
そう、丁度、今日みたいに真夏の熱気を閉じ込めたような夕暮れ時だった。
家が近所ということもあり、花道は流川の面倒をよくみていた。
それは、流川母から熱心に頼まれて仕方なく、というのもあったが、それだけではなく、誰にも感情を表さない流川を自分がどうにかしてやりたいと思ったからかもしれない。
とにかく花道は、幼心に流川を更生してやろうと奮闘していた。
寝汚い彼を毎朝起こしに行ったり、教室で机に突っ伏している姿を見かけては校庭に連れ出したり、クラブ活動なんかでは同じバスケットクラブに入部させたりもした。
そうして花道は、流川にできるだけ活発的かつ子供らしい生活を身に付けさせてきたのだ。
…それが、逆効果になってしまうとも知らずに。
花道がそれに気付いた時には、最早流川は常軌を逸していた。つまり、花道にしか懐かなくなってしまっていたのだ。
そして、
「おい、ルカワ、」
シャツの裾を引く流川に堪えかねて思わず漏らしてしまった一言。
「お前オレとばっかいないで少しはクラスのヤツらと遊べよ」
それが、その後の花道の運命を変えた。
流川は表情を一変し、小四とは思えぬ形相で花道に凄んだのだ。
「オレは他のヤツには興味ねー。昔からそうだ。自分から関わりたいとも、関わって欲しいとも思ったことはねー。でもてめーは別だ、どあほう。」
あまりの展開に花道は面食らった。
というかコイツ、こんな顔もできんのか…
「オレはてめーがいい。てめーがいねーとイヤダ」
「ちょ、ま…待て!」
「イヤダ」
「だから違くて、っあーもう!別にオレはいなくなったりしねーよ!そうじゃなくてだな、」
「イヤダ。てめーが離れるっつーなら、オレもう学校いかねー」
「おま…っ!」
それから流川は小さな両腕で花道にしがみつき、花道がわかったと観念するまで離さなかったのだ。
一人っ子の花道にとって、二つ下の流川は弟のような存在であり、また流川も花道を兄のように思っていたのだろう。
花道はそう決定付け、流川の度を超えた執着を許してしまった。
実際自分も、そこまで必要とされる事に悪い気はしなかったからだ。
―こうして、現在に至る。
あれから四年の経緯を経てやっと、花道は流川を理解した。
コイツはストレスで感情を欠落させるようなタマじゃないと。
それどころか、このガキ。注意深く見ていれば、もの凄く解りやすい表情をするのだ。
つい先日だって―。
思い返して花道は赤面した。
両親の転勤について行けと散々説得する花道に、流川はあの日と同じ表情で拒んだのだ。
てめーがいい、てめーがいないとイヤダ、と。
それから花道へ向かって言った言葉。
あれは…
「どあほう、鍋、吹いてる」
そう、鍋。
…じゃなくて!
「うぉあっ!」
吹きこぼれる湯に、深層深く漂っていた思考が一気に浮上した。
慌てて火を消す花道の後ろで、流川が生意気に笑う。
「なに笑ってんだよ」
「かわいー」
「アァ!?」
「かわいーと思って」
「おま、えは、ほんと…」
年上をからかうとはいい度胸してんじゃねーか!叫ぶ花道に、やはり流川は笑ったままだ。
その上、あろう事かこちらに近寄ってきた。
「かわいーからかわいーって言った。キスしていー?」
ゴスッ!
本日二度目の頭突き。
何がどうなってこんな風に育ったのか、流川は四年の月日を経て、変態へと進化を遂げていた。
やれ可愛いだの、キスしたいだの、どう考えてもおかしい言動をとる。
コイツはほんとに中学生なのだろうか。
…というか、正常な男子なのだろうか。
「今度そーいう事言いやがったら殺す!」
一抹の心配を胸に、花道は今日も流川に鋭い釘を刺すのだった。
next 2
無料ホームページ 楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円]![]() 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!
海外格安航空券 海外旅行保険が無料!